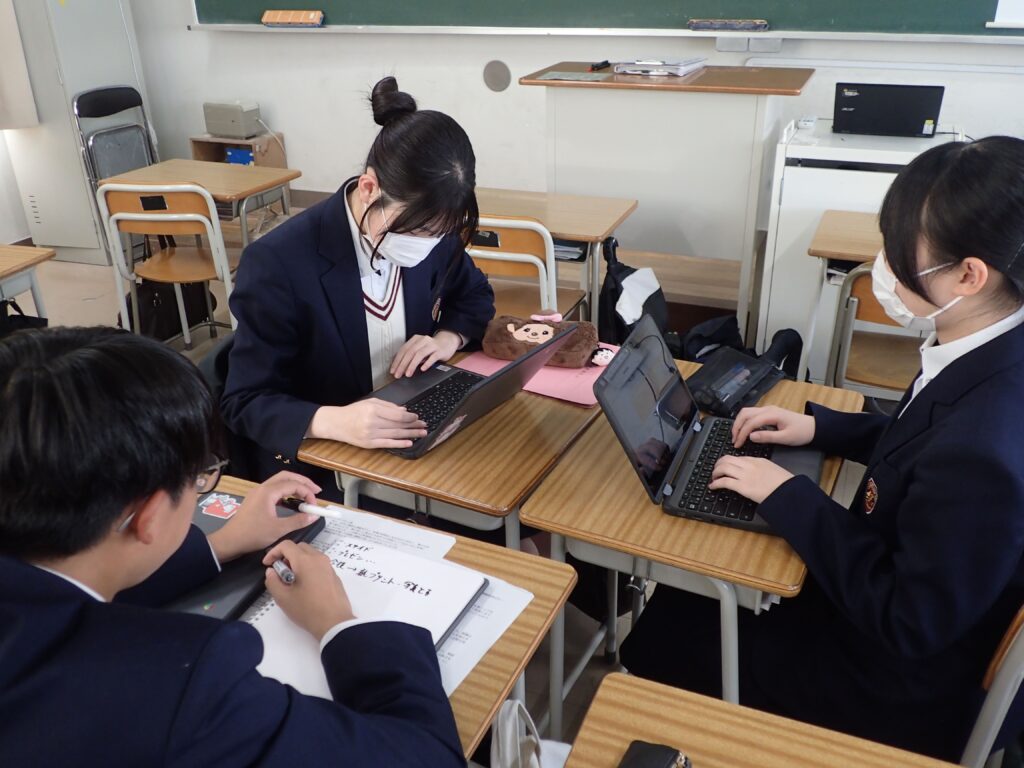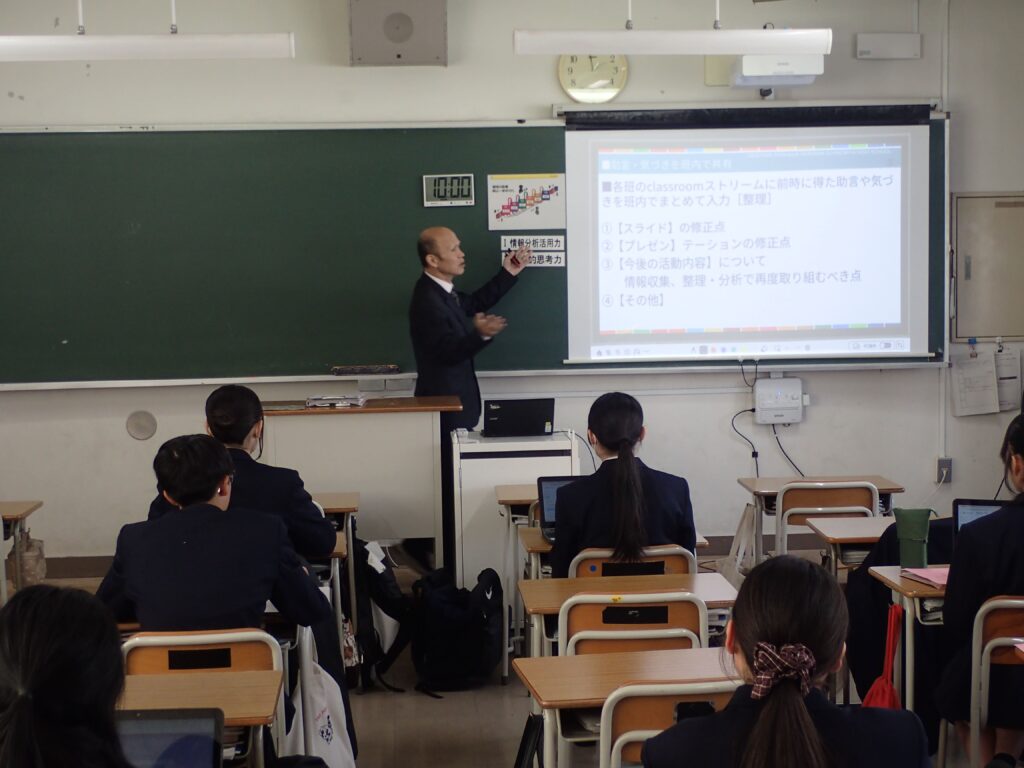11月7日(金)、2年普通科の医療分野では、課題探究の途中経過を“あえて公開する”という、非常に先進的で、探究の核心をつく授業が行われました。
医療系を志望する生徒たちは、10月29日の「分野別発表会」で専門家(山形先生)からいただいたアドバイスをもとに、自分たちの研究をどのように改善するかを考え、再構成する作業に取り組みました。
研究が完成していなくても公開する。
それを材料にしてさらに深める。
ここに、一宮高校が大切にする「探究の本質」がくっきり表れていました。
プロからの助言を“自分の探究”に返していく時間
授業は、まず本時の目標の確認から始まりました。
「助言を“修正点”として受け取り、研究の質を高めるために再構成していこう。」
生徒たちは、先日の講評でメモした内容をClassroomに入力しながら、
どこが弱いのか
研究の目的が曖昧になっていないか
データや資料の扱いは適切か
といった視点で、自分たちのプロジェクトを客観的に見直していきます。
医療分野ならではの“倫理”“信頼性”“妥当性”という観点が、自然に議論の中に出てくるのが印象的でした。
Classroomで共有し合うことで、「探究の質」が目に見える
授業者は、生徒たちの作業を見守りつつも、
「比較できること」「他者から見られること」「言語化すること」
を大切にしていました。
今回の授業で特徴的だったのは、
全てのグループが助言→修正点→改善案をClassroomで共有する
という点です。
研究段階の途中であっても、互いに作業を可視化し、
「この改善案いいね」「その視点は盲点だった」
といった声が次々にあがっていました。
探究が“個人作業”ではなく、“チームとチームの相互作用”で深まっていく。
まさに一宮の探究文化そのものです。
助言をどう「整理」し「構造化」するかに、探究の技術が表れる
整理フェーズでは、
- スライドをどう改善するか
- プレゼンの根拠をどう補強するか
- どの情報を追加・削除すべきか
- 研究の問いそのものを修正すべきか
など、医療研究の本質に迫る思考が生徒の中で動き始めました。
中には、
「このデータは信頼性が弱いので採用しない」
「提示順序を変えることで伝わる構造が変わる」
といった高度な判断をしているグループもあり、探究力の成熟を感じました。
“途中公開”の勇気が、研究者としての姿勢を育てる
今回の授業の大きな価値は、
「未完成の研究を他者に晒し、助言を受けて改善する」
という姿勢そのものにあります。
これは、大学や研究機関でも行われる“ピアレビュー”の考えに近いものです。
- 完璧でなくていい
- 誰かに見せるからこそ気づきが生まれる
- 改善する余地を言語化することで、探究が深まる
一宮高校の探究が“研究文化”として根付き始めているのを強く感じました。
これからが本番 ― 12/12の中間発表に向けて
授業のまとめでは、授業者がこう語りかけました。
「修正点を明確にしたら、それを“次にどう活かすか”が探究です。」
生徒たちは、11/21・11/28の班別ゼミに向けて、
どの改善案から着手すべきかを決め、Classroomに入力していました。
医療分野の探究だからこそ、
論理性・倫理性・正確性が求められます。
この探究姿勢を大切にしながら、12/12の中間発表へ一歩ずつ前進していきます。
課題探究を公開する学校、その強さ
今回のチャレンジは、単なる作業ではありませんでした。
むしろ、
- 研究の途中でも見せる
- 助言を恐れず受け取る
- 自分たちで改善し、次の行動につなげる
という、“研究者としての姿勢”を育てる貴重な機会でした。
「探究の過程そのものを学ぶ」
これは一宮高校の強みであり、こうした文化が生徒たちの未来を大きく支えていきます。