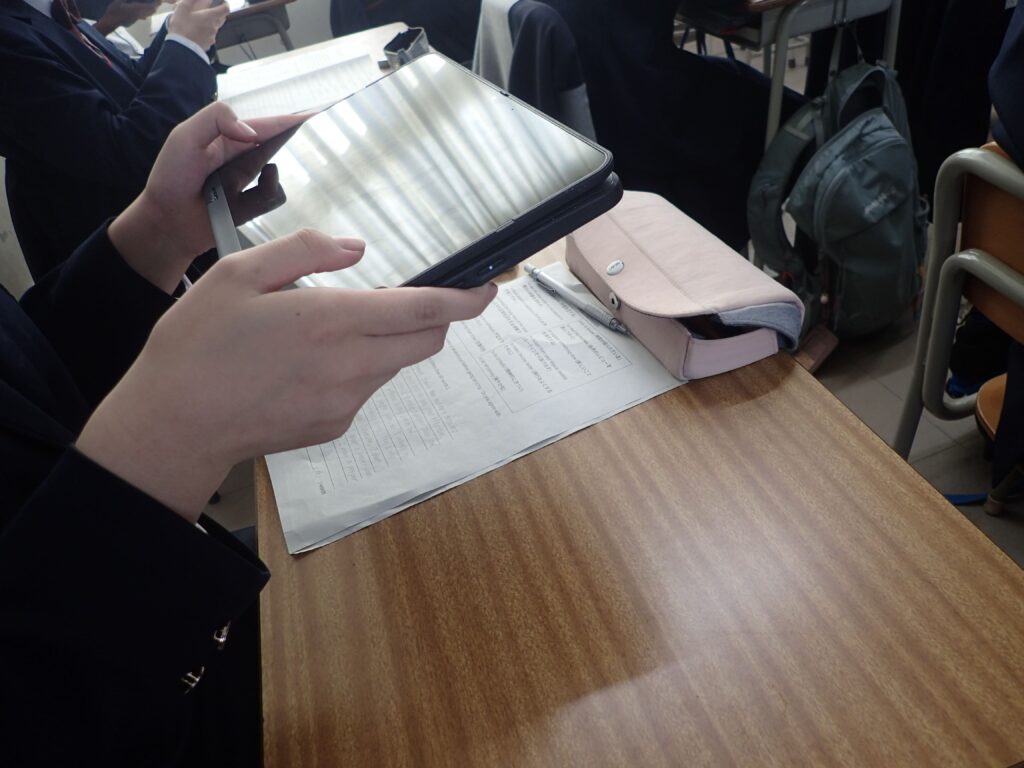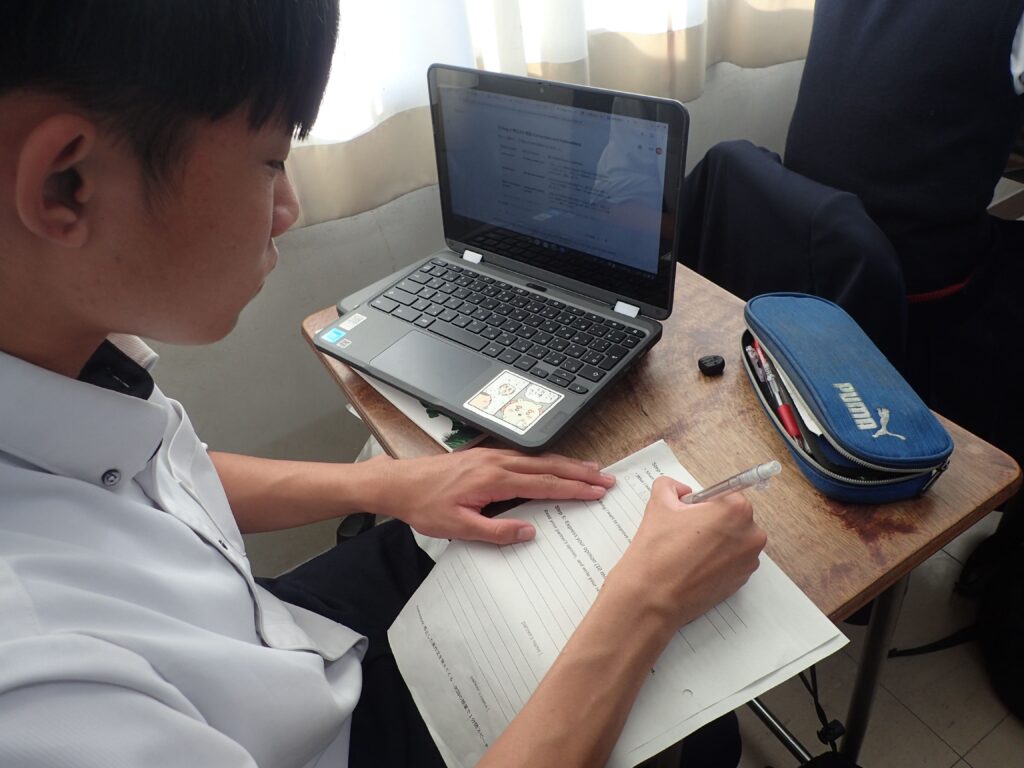11月6日(木)、2年3組では、「EARTHRISE English Logic and Expression II」の授業が行われました。
テーマは “Visiting a new place”。
生徒たちは、英語で「立場を持ち、理由を述べ、賛成・反対の意見を構築する」力を養う探究的な学習に取り組みました。
一宮高校が大切にしている探究6段階(気づき→計画→実行→整理→考察→発表)のうち、今回特に焦点となったのは
“考察・整理”のフェーズ。
生徒自身が過去に書いた英文をAIとペアで見直し、論理の質を高める活動が中心となりました。
学習のスタートは「自分の英文を客観視する」ことから
授業冒頭では、本時の目標を確認し、授業者がこう語ります。
「英語を書くことは、自分の考え方を磨くことでもあります。」
生徒たちは、自分が以前書いた英文を手元に置き、
「どの理由が弱いか」「根拠の提示は十分か」「反対意見へ配慮があるか」
といった視点で読み直しました。
ただ文法を直すだけではなく、
“自分の主張を論理的に整える”
という、言語探究の姿勢が教室に広がります。
ペア&生成AIで英文改善 ― 協働で論理が磨かれる
次のステップでは、ペアで英文を交換し、互いにフィードバック。
「ここは説明が急に変わっているよ」
「例示が弱いから具体例を入れるといい」
といった声が自然に飛び交います。
さらに今回は、生成AIも“第三の相棒”として活躍しました。
AIは文法ミスだけでなく、
・論理のつながり
・段落構成
・主張の明確さ
などを指摘してくれます。
生徒たちは、AIの助言に納得できるものとできないものを吟味しながら、
“自分の判断でもう一度書き直す”
という高度な探究プロセスを踏みました。
振り返りで見えた「論理的思考の成長」
書き直した英文をもとに、さらに深い振り返りが行われました。
「AIの助言に全部従うのではなく、自分で判断することが大切だと思った」
「反対意見への理解を書き加えたことで文章が説得力を増した」
「根拠を具体化すると、主張の重みが全然違うと気づいた」
こうした声から、
英語を書くこと=思考の探究である
という気づきが確かに育っていることがわかります。
他者の英文から学び、自分の意見を再構成する
授業後半では、他者の英文を読み、
「この理由づけは納得できる」
「この反論処理は上手い」
など、相手の文章を材料に“自分の論理を広げる”活動が行われました。
英語の授業でありながら、まるで国語科の評論文のように、
他者の思考を取り込みながら自分の考えを磨く、まさにSTEAM的な言語探究
が展開されました。
英語 × 論理 × 探究が融合する一宮ならではの授業
今回の学びには、次の特徴が見られました。
✔ 自分の文章を「思考」として見直す姿勢
✔ ペア・AI双方との協働で論理を多面的に検証
✔ 記述を通して自分の立場を強化
✔ 探究6段階の“整理・考察”を英語で実践
単なる英作文ではなく、
「英語を使って、自分の考えを世界に伝えるための準備」
としての学びが深まりました。
授業者の問いかけは英語の枠を超えて、生徒たちの思考そのものを揺さぶっていたように感じます。